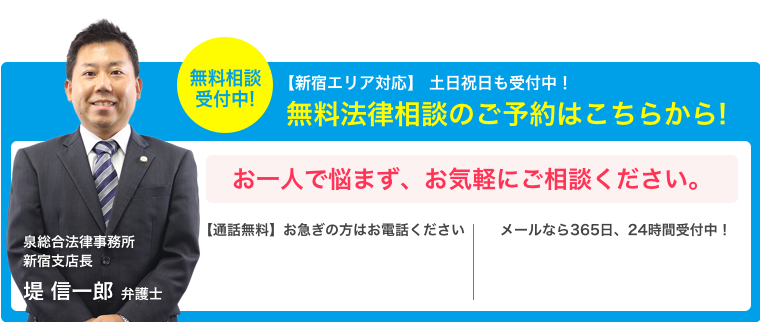暴行罪で逮捕された家族を釈放してほしい

家族が暴行罪で逮捕された。本人だけでなく、ご家族も、少しでも早い釈放を願うことでしょう。
この記事では、次の2点を解説します。
- 暴行罪で逮捕された被疑者が釈放されるのは、どのような場合か?
- 釈放されるために、ご家族は何をするべきか?
このコラムの目次
1.暴行罪はどのような犯罪か
暴行罪(刑法208条)は、人の身体に物理的な有形力を行使する犯罪です。
殴る蹴るの暴力をふるう行為が代表的ですが、直接的に身体に触れなくても、身体に向けられた行為であれば足ります。その行為が直接身体に害を及ぼす可能性がごく少なくとも成立します。
それゆえ、足元に物を投げつける、有害ではない粉や液体を浴びせかける、拡声器を耳もとに近づけて大声を出す、高速道路で幅寄せ走行をするなどの各行為も、暴行罪で処罰された裁判例があります。
暴行罪の法定刑は、次のとおりです。
- 2年以下の懲役
- 30万円以下の罰金
- 拘留(1日以上30日未満の身体拘束)
- 科料(千円以上1万円未満の罰金)
暴行の結果、被害者が怪我を負ってしまうと傷害罪(204条)となり、法定刑が15年以下の懲役又は50万円以下の罰金と厳しくなります。
暴行罪で逮捕されても、後に被害者から怪我をしていたという診断書が提出されて、傷害罪で立件されるケースは珍しくありませんから、逮捕容疑が暴行罪だったからといって軽く考えることはできません。
2.逮捕された後の手続
暴行罪で逮捕された後の刑事手続の流れは次のとおりです(以下の条文は刑事訴訟法)。
逮捕後、警察での取り調べを受けます。取り調べ以外の時間は警察の留置場で過ごします。逮捕から48時間以内に身柄を検察庁に送られます(203条)。これを検察官送致といいます。マスコミ報道では「送検」と呼ばれています。
検察庁でも、検察官からの取り調べを受けます。検察官は被疑者の身柄を受け取ったときから24時間以内かつ逮捕から72時間以内に、①ただちに起訴する、②釈放する、③裁判所に勾留請求をする、の3つの選択肢の中から、どれを選ぶかを決めなくてはなりません(205条)。
検察官が被疑者の身柄を拘束しての捜査が必要であると考えた場合には③勾留請求が選択されます。しかし、暴行罪は刑法に定めのある犯罪の中では軽いほうですから、身柄拘束をする法律上の要件が整っていたとしても、検察官が拘束による被疑者の受ける不利益を考慮して②釈放する選択がなされることも時にはあります。
検察官が裁判所に勾留請求をした場合、被疑者は裁判所へ連れて行かれ、裁判官からの勾留質問を受けます。裁判官が勾留の理由と必要性があると判断すれば勾留を決定します(207条、60条、61条)。
検察官が勾留を求めても裁判官が認めないケースは最近増えていますが、それでも多くの場合では認められることになります。
勾留される期間は、検察官が勾留請求をした日から10日間ですが、必要性があれば、さらに10日間を限度として延長を請求できます(208条)。
最初の10日間で完全に捜査が終了し処分方針も決まった、あるいは示談が成立し処分しないことに決まったなどの事情があれば期間満了とともに釈放されることもありますが、多くの場合、捜査未了を理由として検察官が延長を請求し、裁判官によって認められます。
こうして、勾留請求した日から20日間、逮捕した日からは23日間(72時間プラス20日間)が、最大限の勾留期間となります。
この23日間の間に、検察官は①起訴する、②不起訴として釈放する、③処分を保留したまま釈放する、の3つの選択肢の中から取扱いを決めなくてはなりません(208条)。
被疑者が起訴された後は、被告人という立場に変わり、拘置所に移されて身柄拘束が継続します。これを被告人勾留といいます。被告人勾留は起訴の日から2ヶ月を期限としますが、1ヶ月ごとに更新されます(60条2項)。
もっとも、起訴後は保釈請求が可能です。裁判官によって保釈が認められれば、保釈金と引き換えに身柄を開放してもらえます(89条)。
起訴された日から1~1ヶ月半程度で最初の裁判が開かれることになります。
さて、以上の手続の流れの中で、逮捕された被疑者が釈放され得る場面がいくつかありました。これを分けて説明しましょう。
3.逮捕後、検察官送致前に釈放される場合
逮捕された後、身柄を検察に送致されることなく釈放してもらえる場合には、次の2つがあります。
(1) 警察が留置の必要性がないと判断して釈放
ひとつは、警察によって留置の必要がないと判断された場合です。
警察は被疑者を逮捕した場合でも、「留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放」しなくてはなりません(刑訴法203条1項)。身柄を検察官に送致されることなく釈放してもらえるのです。これは現行犯逮捕でも同様です(同216条、199条)。
実際、平成29年の警察庁統計(※)では、暴行で現行犯逮捕された4795人のうち、約23%にあたる1116人は身柄を検察官へ送致されることなく釈放され、在宅事件として書類送検だけされています。つまり暴行の現行犯で逮捕されても、4人に1人弱は身柄を解放されるのです。
同様に、暴行で現行犯ではなく逮捕状による通常の逮捕がなされた2246人のうち、約6.4%にあたる144人は身柄を釈放されて、書類送検だけとなっています。
※警察庁「犯罪統計書・平成29年の犯罪」254頁・第31表「罪種別・身柄措置別・送致別検挙人員」
(2) 警察が微罪処分として釈放
もうひとつは、微罪処分です。
微罪処分とは、検察が特に指定した事件については、検察へ事件を送致する必要がなく、お説教をするだけで釈放するという制度です(刑訴法246条但書、犯罪捜査規範198条~200条)。
微罪処分となる条件は、検察庁が通達で定めますが、概要は次のような場合です。
- 被害額が僅少
- 犯情が軽微(悪質でない)
- 被害の回復が行われた(盗品の返還や、弁償金・慰謝料などの支払い)
- 被害者が処罰を希望しない
- 偶発的犯行で再犯のおそれがない
- 刑罰を必要としないと明らかに認められる
参考文献:「刑事訴訟法(新版)」田宮裕・有斐閣157頁
前出の平成29年の統計では、暴行で検挙されたが逮捕されなかった1万8642人のうち、約64%にあたる1万1986人が微罪処分とされています。
それだけでなく、暴行で現行犯逮捕された4795人でも、そのうち僅かですが55人は微罪処分となっているのです(※)。
※前出、警察庁「犯罪統計書・平成29年の犯罪」254頁・第31表「罪種別・身柄措置別・送致別検挙人員」
4.検察官送致後に釈放される場合
では、検察官送致されてしまった後に釈放されるのは、どのような場合でしょうか。
(1) 検察官が留置の必要がないと判断して釈放
ひとつは、検察官によって留置の必要がないと判断された場合です。
検察官が送致された被疑者を受け取ったときは、留置の必要性があると思料するときは、直ちに起訴するか、勾留請求をしなくてはならず、「留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放」しなくてはなりません(204条1項)。
平成29(2017)年の検察庁統計(※)では、暴行罪で検察が身柄を受け取った5751人(但し、検察官が逮捕した5人を含む)のうち、約21%にあたる1221人が検察官によって釈放されています。
※2017年検察統計調査
表番号17-00-41「罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員」
(2) 裁判官が勾留の理由がないと判断して釈放を命令
検察官からの勾留請求に対して、勾留するかどうかを判断するのは裁判官です。被疑者が犯罪を行ったことを疑うに足りる相当な理由があり、身柄を拘束する必要性があることが勾留の要件です。
相当な理由とは、法が定める①住所不定、②罪証隠滅(捜査妨害)の恐れ、③逃亡の恐れのいずれかです。拘束の必要性は、被疑者の負う不利益が明らかに大きすぎる場合などに、それが認められないという形で判断されることがあります。
裁判官が勾留の理由がないと判断する場合は、勾留請求を却下し、直ちに釈放を命じなくてはなりません(207条5項)。
前出の平成29(2017)年の検察庁統計(※)では、暴行罪で検察が勾留請求をした4371人のうち、約11.6%にあたる454人の勾留請求が却下されています。
※前出の表番号17-00-41
5.勾留された後に釈放される場合
(1) 準抗告で勾留決定が取り消される場合
裁判官によって勾留決定されてしまっても、準抗告という不服申立て手段で争うこともできます(429条1項2号)。
準抗告を申立てると、同じ裁判所の別の裁判官があらためて勾留の可否を審査し、勾留する理由がないと判断すれば、最初の勾留決定を取り消したうえ、検察官の勾留請求を却下することになり、直ちに釈放が命じられます。
ただ、いったんなされた勾留決定の準抗告での取り消しは、なかなか認められないのが現実です。先に述べたような、勾留の認められる要件を踏まえた的確な反論と裏付けの用意が必要になります。
(2) 裁判官に勾留延長の理由がないと判断されて釈放
検察官は勾留請求の日から10日間の間に起訴するか、釈放するか(不起訴の場合と処分保留の場合があります)を決めなくてはなりませんが、やむを得ない理由があるときは、最大10日間の延長を裁判官に請求できます。
通常、検察官は「捜査未了」を理由に延長を求めますが、裁判官が延長の理由がないと判断すれば延長を認めないこともできますし、10日間の延長ではなく、もっと短い期間に限って延長を認める場合もあります。
延長が認められなければ、最初の10日間の期間内に起訴できない限り、検察官は釈放しなくてはなりません。
(3) 勾留満期に不起訴を勝ち取って釈放
検察官は勾留期間内に起訴するか、釈放するかを決めなくてはなりません。
犯罪の嫌疑がなかったことが明らかになれば、当然に不起訴となり釈放されます(嫌疑なし)、犯罪の証拠が集められなかった場合も同様です(嫌疑不十分)。
釈放はするが、在宅事件として捜査は続けるという場合もあります(処分保留)。
さらに犯罪の嫌疑と証拠があって起訴できるけれども、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」(248条)といったあらゆる事情を考慮して、あえて不起訴として釈放することもできます(起訴猶予)。
(4) 略式起訴で釈放
起訴には、被告人が公開の法廷で裁かれる公判請求と、法廷に出廷する必要はなく簡易裁判所の書類上の手続で罰金を納めるだけで済む略式命令請求(461条)があり、前者を正式起訴、後者を略式起訴と呼びます。
どちらの手続を求めるかは検察官が判断しますが、略式起訴をするためにはそれを受ける被疑者が略式手続にすることを承諾していることが条件とされています(検察官は取り調べの終了後にその旨を認める書面を作らせます)
勾留中の被害者が略式起訴される場合は、被疑者を検察庁に待機させて略式起訴を行い、即日、裁判所が略式命令を発令したら、被疑者を裁判所に連行して命令書を受け取らせ、検察庁で罰金を納めさせて釈放するという扱いが通常です(在庁略式)。
6.釈放されるために、家族は何をするべきか?
暴行罪で逮捕された後の手続とその間に釈放される場合は上のとおりです。逮捕されてから裁判となるまでの間に、釈放される可能性のある機会は何度もあることが、おわかりいただけたと思います。
その機会を生かすために、ご家族ができることが2つあります。
(1) 面会・差し入れ等で被疑者を励ます
ひとつは面会、差し入れ、手紙を通じて被疑者を励ますことです。
被疑者が無実を主張している場合にはその意に反して罪を認めることがないよう元気づけ、また事実を認めている場合には捜査に協力することを促したり家族が更生の支援をする意思があることを示したりという形で被疑者の利益を図ることができるでしょう。
しかし、ご家族を含めた一般の方々が被疑者に接触する機会は限られており、回数、時間、日時、差し入れ可能物品は捜査機関側の都合で制限されるうえ、裁判所の決定により完全に遮断されてしまうこともあります。ですから、刑事手続にご家族の及ぼし得る影響力はどうしても小さくなってしまいます。
もうひとつは弁護士を選任することです。
(2) 早期の釈放を勝ち取るために弁護士を選任
弁護士は被疑者の利益を守る刑事弁護人となれる唯一の職業であり、刑事事件の専門家です。
暴行事件で逮捕されたケースでは、警察の段階で留置不要と判断されるか微罪処分とされれば、逮捕から48時間以内に釈放してもらえます。
また検察官に勾留請求は不要と判断されれば、逮捕から72時間以内に釈放してもらえます。
そのために弁護士が行う弁護活動のうち、暴行の事実が間違いのない事案では、被害者との示談交渉が最も重要です。
被害者と示談交渉を行い、相応の示談金を受け取ってもらい、示談書に「処罰を望まない」、「寛大な処分を望む」、「宥恕する」といった宥恕文言(宥恕(ゆうじょ)とは、寛大な気持ちで許すという意味です)を記載してもらい警察や検察に提出するのです。
これによって、暴行の被害が回復した(賠償された)こと、被害者の処罰感情が無くなったことが明らかになります。
同時に、当事者間では決着がついた以上、被疑者が逃亡したり、証拠隠滅を図ったりする可能性もなくなったと言えます。
このため早期に示談を成立させて示談書を提出することは、警察に留置の必要がないと判断させること、微罪処分として扱うと判断させること、検察官の勾留請求を思いとどまらせることに役立つのです。
もちろん、示談交渉は相手のあることですから、速やかに成立することが常に期待できるわけではありません。ですが、弁護人を立てて示談交渉を進めているということそれ自体が、事実を認め争う意思がないこと、平和的な解決を目指しており被害者に危害を加えるおそれが少ないこと等、身柄拘束を阻止しまたは早期に終わらせるために有益な事実を裏付けることになります。
仮に示談成立に至らなかった場合でも、反省の態度を示し賠償の意向を示したことに一定の評価は得られます。示談交渉を試みたことが全く無意味に終わるようなことはまずありません。
7.弁護士を選任する理由
では、示談をするために弁護士を選任しなくてはならない理由はなんでしょうか?
理由は4つあります。
(1) いつでも接見が可能
逮捕の48時間は、弁護士以外は誰も被疑者と面会できません。家族らであっても、本人から事情を聞くこともできないので、示談交渉をしたくても、どうしようもありません。
弁護士であれば逮捕中も、土日祝日、夜間でも直ちに面会(接見)することができます。
(2) 示談交渉を着実に進められる
被害者と面識のない場合、示談交渉をしたくとも連絡先がわかりませんが、警察・検察は、被疑者やその家族などに被害者の氏名・連絡先を教えることは絶対にありません。プライバシー保護とお礼参りなどによるさらなる被害を防ぐためです。
しかし、弁護士に限っては、警察・検察は被害者の同意を得たうえで、連絡先を教えてくれるのです。つまりこの場合では弁護士を選任しない限り、示談交渉そのものを開始できません。
たとえ被害者が知り合いであっても、被害者からすると被疑者の家族等は犯人側の人間です。不安や嫌悪感をもたれてしまい、交渉すらできないことも珍しくはありません。そのような場合でも、弁護士であれば多くの場合、交渉に応じてもらえます。紛争解決の専門家を間に立てることは、真摯に平和的解決を望んでいるという意思を被害者に示す効果もあるためです。
示談交渉は、被害者側が圧倒的に強い立場での交渉です。残念ながら被疑者側が身柄解放や不起訴処分を望んでいるのに乗じて高額の示談金を要求してくる場合もあります。家族らでは、その要求が不当なのかどうかの判断も迷うでしょう。
そのような場合でも、弁護士は暴行事件の示談金の適正な相場額を知っていますから、多くの場合、妥当な金額で解決するよう被害者を説得することが可能です。
このような理由から、弁護士を選任してこそ、早期の適正な示談成立が期待できるのです。
(3) 検察官送致後でも釈放が早まる
検察官送致された場合でも、弁護士は早期釈放を目指して、事案に応じて以下のような弁護活動を行います。
- 検察官と面談し、あるいは書面を提出し、勾留の必要性がないので勾留請求をしないよう要請する
- 勾留請求されたら、裁判官と面談し、また書面を提出する事で、勾留請求の却下を要請する
- 勾留決定されたら、準抗告を申し立て、取り消しを求める
- 勾留延長の請求がされたら、裁判官に対し延長を認めないよう要請する
- 被疑者に有利となる諸々の事実とその裏付け証拠を集め、検察官に対し不起訴とするよう要請する、あるいは起訴がやむを得ない事案であっても略式命令請求とするよう要請する
- 正式起訴されてしまったら保釈申請を行う
これら釈放されるチャンスの各段階でも、被害者との示談が成立しているか否かが大きく影響します。
さらに仮に公判請求をされてしまった場合でも、示談が成立していれば、量刑で有利な事情として斟酌され、刑が軽くなったり、執行猶予を得られたりする可能性が高くなります。
8.まとめ
暴行罪の場合、多くは略式命令での罰金刑ですが、これも前科となる点では懲役刑と変わらないので、避けるに越したことはありません。
以前にも同様の行為で逮捕されたことがあったり有罪とされたことがあったりすると、正式裁判の上での懲役刑を含め厳しい処分も考えられます。
刑事処分による不利益を避けるためには、釈放されるだけでなく、不起訴処分を勝ち取る必要があるのです。
暴行事件で逮捕された場合、直ちに弁護士を選任して、示談交渉などの弁護活動を開始することが、早期の釈放や有利な処分を勝ち取ることにつながります。
暴行事件でお悩みの方は、数多くの刑事事件を担当してきた泉総合法律事務所に、是非ご相談ください。
-
2019年9月12日刑事事件 痴漢で逮捕されたらどうなる?家族が弁護士に依頼するメリット
-
2019年8月15日刑事事件 痴漢で勾留されたらどう対処すべきか
-
2019年8月27日刑事事件 家族が強制わいせつ罪で逮捕された場合にできること